諸隈元著「人生ミスっても自殺しないで、旅」に
「どんな言葉も嘘くさかった。」
というくだりがある。戦争に関する知識を字面で垣間見、現地の旅情に感傷を仮託している著者自身の罪悪感の吐露だ。酒を飲んだ帰りの地下鉄で読みながら、言い様の無い心持になり、胸が詰まった。サラエヴォの事はよく知らないが、調べればおそらく正確で公正な情報を得られるだろう。あとは時間の問題だけだ。そして、ウクライナの事も分からない。時間の問題にしているという怠惰のせいもあるが、不安定な情報の移ろいの中に黙って身を置くという勇気が出せないためでもある。だが、そうも言っていられなくなって来たらしいから、こうして書き出した。
Shunメンバーのツイートに
「そしてこの有事に自分は何ができるんだろうとも考えてしまう。」
とあったのだが、私には今が『有事』であるという自覚が無かった。過渡期でなかった現代など、過去のどの現代にも無く、それは現代にもあてはまるという自覚はあるが。『何ができるんだろう』という感覚も同じく、一寸の虫にも五分の魂程度である。言い換えれば、有事だろうと平事だろうと、人類愛を根底においた自己実現を日々更新すること。西田幾多郎の説を蟻んぼにでもなったつもりでやっている。
そこにShunメンバーは一線を画してしまった。さあ、これはうかうかしてはいられない。さらにここへ来て、冒頭の字面が私を戒める。実現性と現実性を兼ね備え、実行の勇気を奮い立たせて行動できることは何か。自衛隊のウェブサイトで予備役の募集を読んだ。だが、駄目だった。申し込めるのは三十四歳までだった。死んだ母方の祖父に手を合わせる思いがした。彼は出征予定の前年に終戦を迎えていたからだ。父方の祖父は満州でスナイパーをしていた。嘘くさく感じられることなく、かつ実現できそうなことは他に思いつかなかった。
話は逸れるが、利休と秀吉の対立に興味を持ったのがきっかけで、マーティン・スコセッシ監督の「沈黙」を観る必要があった。だが、見放題対象外だった。埋め合わせに戦争映画を、なるべくエンタメ色を抑えた、まともなやつを観ようとした。洋画劇場で観たがうろ覚えだったリドリー・スコット監督の「ブラックホーク・ダウン」を選んだ。先日、Shoメンバーと同監督の「エイリアン・コヴェナント」を鑑賞したばかりだったのも選んだ理由の一つかも知れない。
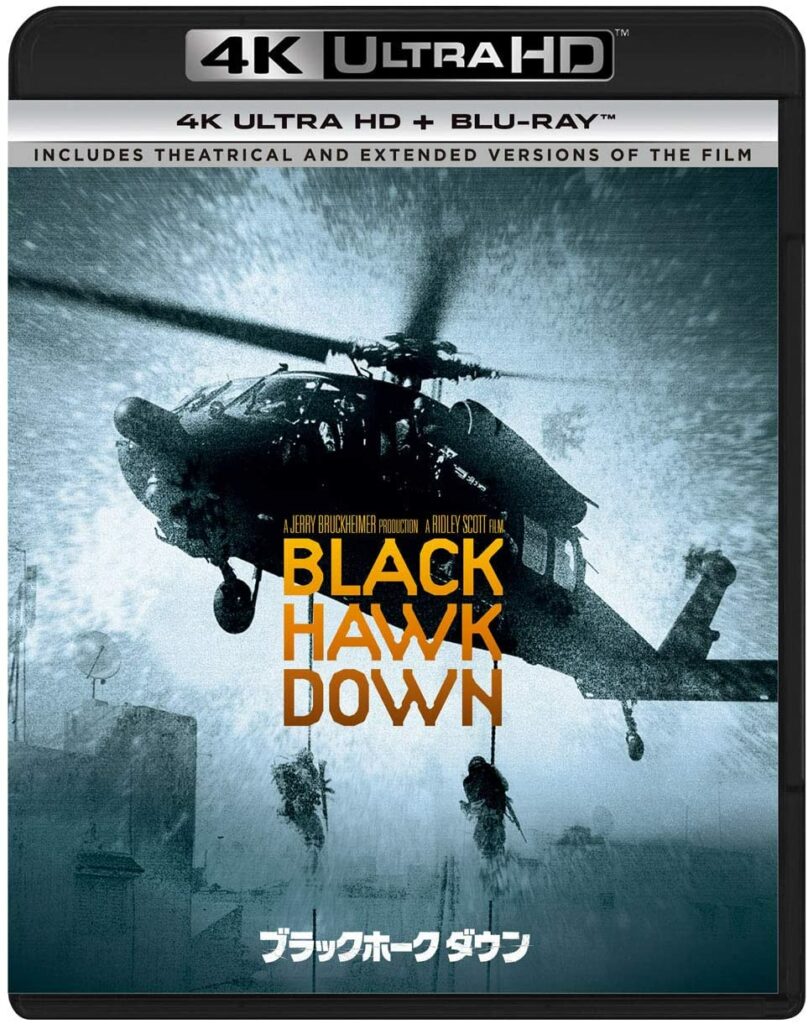
洋画好きなら誰もが安心するであろう、ウィリアム・フィクナーだ。信頼感のあるマッチョな隊長を演じている。キャスト一覧を眺めれば、トム・ハーディ、ヒュー・ダンシー。心許せる俳優たちの、奇しくもハリウッドデビュー作だというのが嬉しい。はたして探せるだろうか。そのような気楽な心境でいられるだろうか。
寄せ集め部隊間の軋轢、上官への揶揄、兵卒たちの気の緩み。先行き不安が増してゆく。雲行きが怪しいとはよく言ったもので、MH-60 ブラックホークの行方は燃やされたタイヤから立ち上る黒煙のごとく真っ暗である。非人道的な部族虐殺を断行するアイディード将軍の側近を拉致すべく、空陸百名の三十分で終わるはずの作戦は、夜明けまで十五時間に及んだ。ガンシップ乗員は燃やされているタイヤが、彼らに向けられた煙幕であることに気付かない。地上部隊を足止めするバリケードは、既に随所に張り巡らされていた。合流の遅延が、部隊へ致命の一撃を撃ち込む。
「誰も置き去りにするな。」
私はありきたりな言葉を聞かされたくないのだが、これには説得力があった。そして、百人の部隊はそれを実行する。命令を出す少将も、実現のために様々な手立てを打つ。どんな言葉も嘘くさいから、映画で展開される実行の勇気に胸が詰まる。無論、米国視点の正当化、米軍礼賛と言われればそれまでなのだが。
市街戦の巻き添えで人がばたばたと死んでいく。映像が私の眼を通過したせいで、死が数字に変わってしまうから何も感じない。戦争の何が嫌かって、人々の死を株価の下落を通じてしか感じられない人間の多さが嫌なのだ。私も同類だったらしい。こんな言葉も嘘くさくて嫌になる。ここまで書いて、やはり黙っていたかったと思う。さりとて、ただの映画感想文にしてしまうわけにもいかない。
ソマリア連邦共和国は、東アフリカの角状になった半島を領する国家だ。一九七七年、西部に接するエチオピアのオガデン地域のソマリ人たちが、ソマリアの軍事独裁政権が掲げる大ソマリ主義に共鳴し、エチオピア政府に独立のための反乱を起こす。オガデン地域に対しソマリアは軍事支援を行うも、エチオピアをキューバとソ連が支援し紛争状態となる。結果的に、ソマリア側は撃退され大きな損害を受けると共に窮乏が加速。独裁政権は、バーレ大統領自身が属する南部氏族のみを重用し、北部の生産物で得た外貨を南部の開発に充て続けたため、八十年代全般に渡る、バーレ独裁政権への反政府武装闘争を引き起こす。
主要都市は次々に陥落し、九十年には『モガディシュ市長』と呼ばれるまでに大統領の影響力は失墜していた。その翌年、首都も制圧され、バーレは国外追放、さらに北部はソマリランド共和国として独立を果たす(正式には二度目)。しかし結局は、第二の独裁者としてアイディード将軍が就任したに過ぎないのだった。
現在のソマリアは、独立したソマリランドと、東部を接する領土紛争中のプントランド、さらに中南部は四つの自治区となっており、統一されてはいない。ソマリア内戦は現在も継続中だ。この映画は、九二年末に国連が米兵中心の多国籍軍を派遣した後の、九三年十月三日の戦闘を描いている。二千年代には国境を接するエチオピア軍による進行や、米軍の再介入など、まだまだ書き切れないが本筋に戻る。
作品終盤、不純な理由で観始めた私に天罰が下る。洋画劇場でカットされていたであろうシーンだ。ある漫画家の日記漫画で上映当時のこの箇所は知っていたはずだったのだが。直視できず、動画を一時停止し、シャワーを浴びた。嘘くさくても痛みは感じるのだ。他人の不幸は蜜の味だが、身内の不幸は心が痛い。戦争の犠牲者は、他人でも身内でもない。心が痛むのは同じ人間だからだ。ウクライナの事をそんな風に、同じように考えている人たちと共に、私がここに居ることに安堵していても良いのだろうか。
「国に帰りゃ、こう聞かれる。『おい、フート、何で戦う。なぜだ。もしかして、戦争中毒か?』俺はひと言も答えない。なぜか?どうせ分かりゃしない。奴らには理解できない。」
自分自身を全く重ねて見てしまい、嘘くささは最高潮に達した。この感覚を文章に残したくて書き出したのだった。だが、何を悲観する必要があるだろう。自己同一より自己欺瞞、自己実現より自己叛逆。積み上げてきたものを棒に振ることが至上のものであるならば。そうとも、お国や名誉のために戦っているんじゃない。なら俺たちは何のために戦っているのか、ぜひ鑑賞してみて欲しい。
とかくに人の世は住みにくい、と感じてこう思った。嘘くささとは、ラッセルが「幸福論」の前半で、不幸の原因として指摘したうちの『罪の意識』ということではあるまいかと。第一部第七章を読み返す。しかし、僕は悪事の露見を恐れているのではない。もしかすると、僕は僕自身の道徳を疑っているのではあるまいか。
「新しい週が始まる。月曜だ。」
目の前の戦いに馳せ参じる、寡黙な実行者を僕たちは尊敬する。実行するとは意識を殺すことだからだ。誰かではない。
