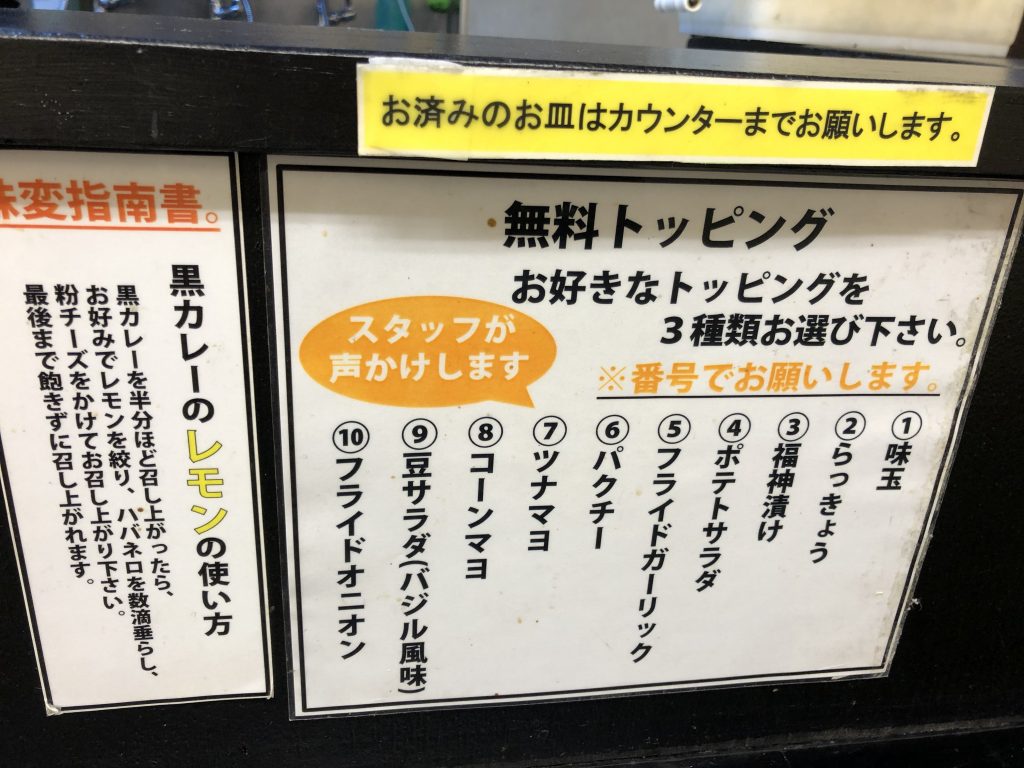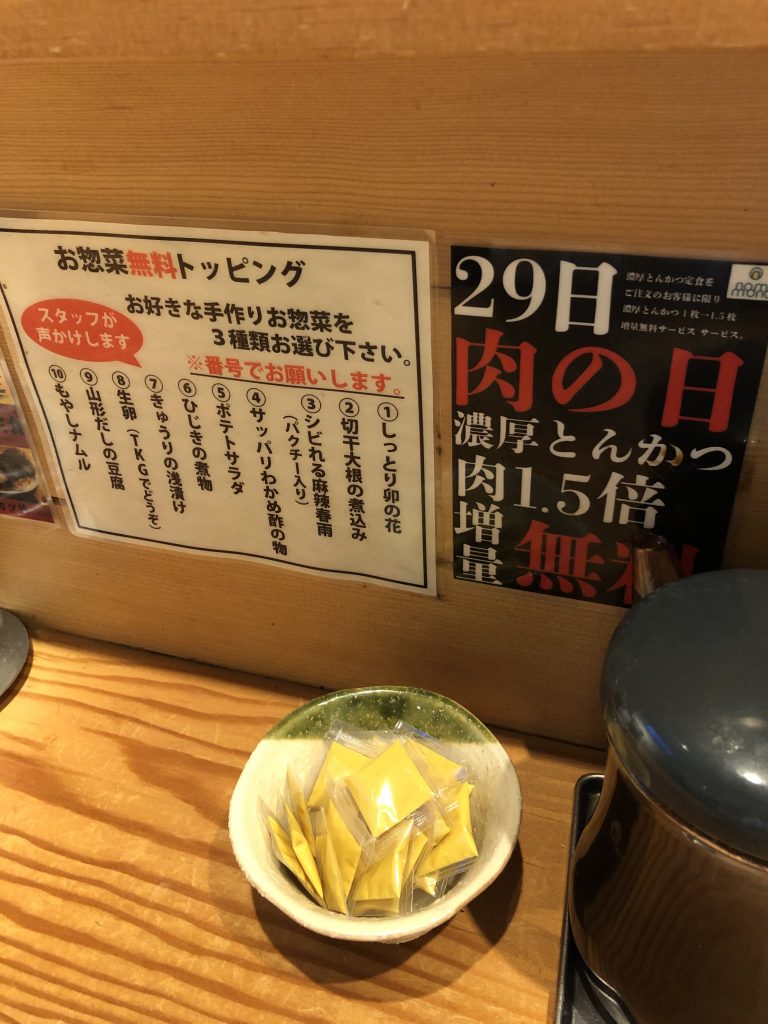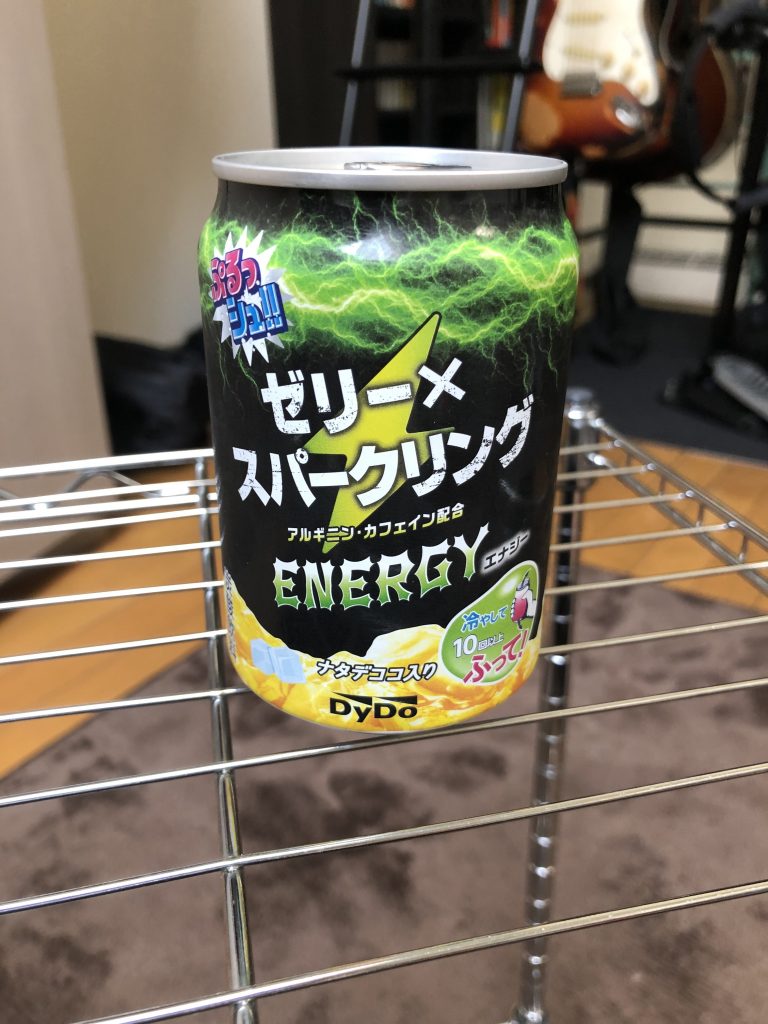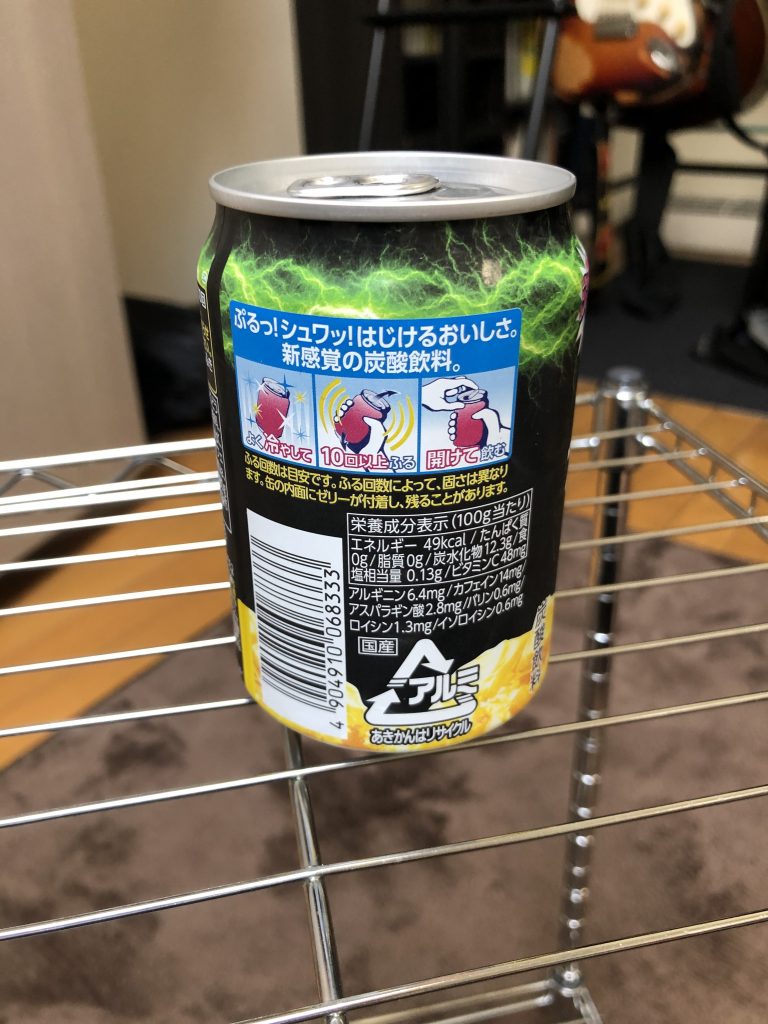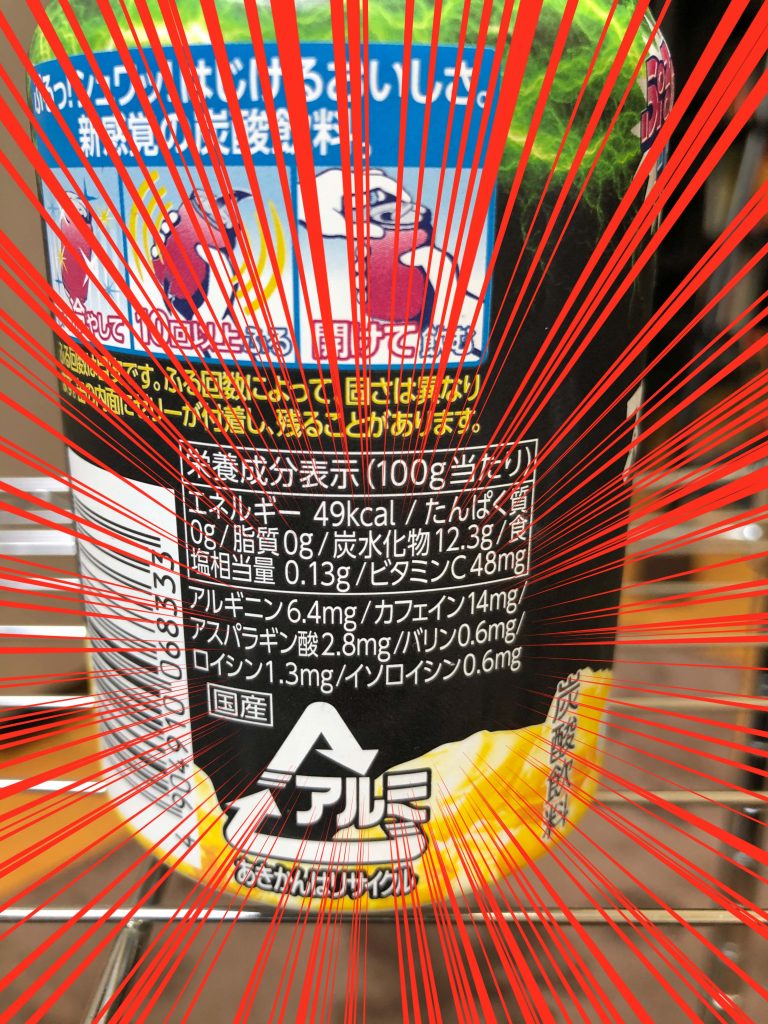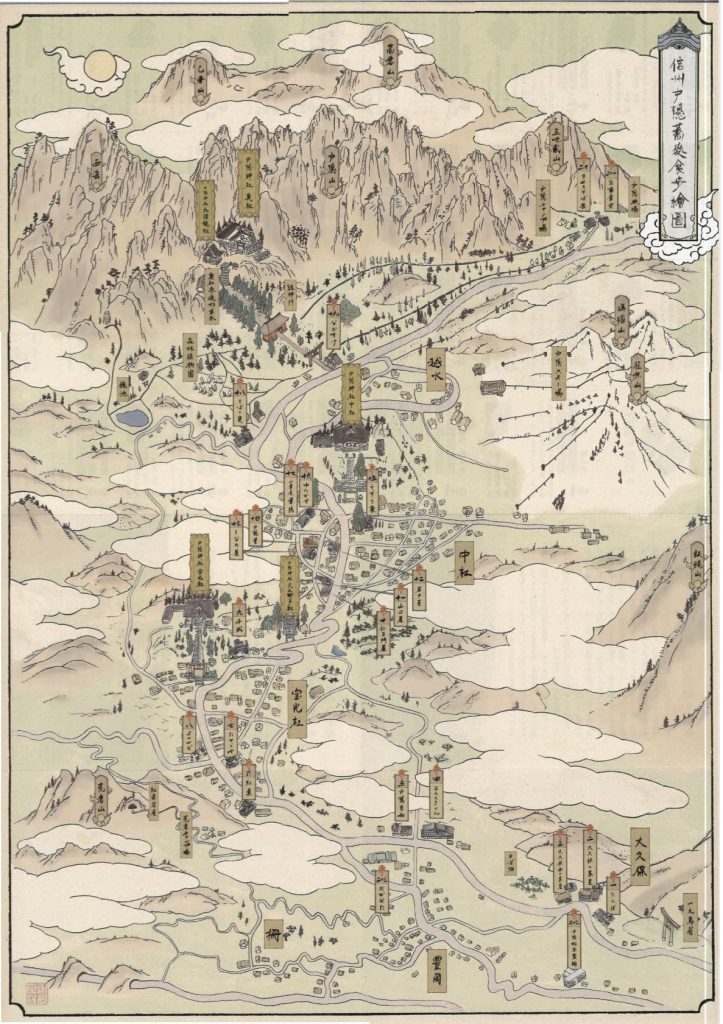作戦開始の時刻まで、まだ余裕がある。そこへ、向こうからセダンが接近して来た。先に到着していた第十一位の面々である。
「待たせるんじゃねえよ、新入りども。」運転席のドアを開けて、大柄で筋肉質な男が眉間に皺を寄せながら言い放つ。タンクトップに、デニムを合わせた色黒の男。いや、男たちが車内からぞろぞろと出てくる。さらに、向こうにももう一台停車している。
第十一位側の認識としては、自軍の数合わせ程度にしか第十二位を見ていない。また、序列的にも見下しているのは当然だった。そして、のこのこやって来たのは理系学部にたまたま混じったような文系連中が四人だ。三人の手下は全員眼鏡を掛けている。落胆と苛立ちが手に取るように分かる。熱せられた飴のように延びた時間の中で、綿摘恭一が考える隙も与えずに、瓜生昇が電光石火で結論付ける。
『此奴ら揃いも揃って野球部出身で御座いって風貌だが、同じ高等教育まで受けた人種のようには到底思えない。それもそのはずだ、俺達が安定した生活を掴み取ろうと当て所もなく勉強に明け暮れていたその頃、此奴らは遊びの延長みたいな部活で散々に人生の夏休みを謳歌して、さて引退したと思ったら下の根も乾かないうちに(下で間違いない)推薦入試で進学バンザイと来やがる。挙げ句の果てが、俺らも此奴らも同じで仲良くヤクザ稼業とは、そんな結末を一体誰が決めやがったんだ。』誰が決めたか知らないことを、瓜生昇は即断で決め付けた。そしてこの男は、一度きりの人生だから、どんな挑発にも応じる。果たしてそれが挑発で無かったにせよ。
「アンタ、そんなことより靴紐が…。」まだ自己紹介も済んでいない大柄の男は、そう言われてジッと足元を見つめる。スニーカーには特段変わり無い。しかし、ふと視線を上げた先にあった光景は、異常だった。名前も知らない新入りの手中に、小型のリボルバーがいつの間にか握られている。目が合った瞬間に瓜生はS&W M60の撃鉄を起こし、一同がその音に気付いて一斉にそちらを注目する。
「バァン。アンタ死んだぜ。」引き金を引けばいつでも殺せる。スーツの袖に隠した電動アームが静かに目覚めたのだった。この場にいる誰かが死ぬまで、それが再びの眠りに就くことは無い。これが、瓜生昇のシューゲイザー。
「手前、何向けてやがる!」金縛りのようになりながら、半狂乱で男が叫ぶ。今までは、いつだって銃口を向ける側だったから。第十一位付きの面々は、まだ銃を身に付けていない。完全に想定外の事態である。まさか、身内に銃口を向けられるとは。
「五月蝿え!こちとら予定より十分も前に到着してんだ!第十一位の序列が上ってだけで、手前達そのクソの周り飛ぶ蝿ほどの存在が!何を上からデカい口ききやがる!無礼に死で報いる礼儀を拝まされてえか!」序列が上であるならば、その構成員たちも上役となるのだが、今この場の瓜生の狂犬さながらの気迫に第十一位付きの一同固唾を飲んでいる。此奴らどう言う教育を受けてるんだと思いつつ、第十二位自身が船橋に来てから日が浅い事までは頭が回らない。
「分かったから、向ける相手はこの中にいる連中だろうが…。」男が、怒り半分呆れ半分という顔で柵の向こうを親指で示す。
鈴井は運転席から姿を現さない。子桜、瓜生に『よっ、肝っ玉』と目配せ。起こした撃鉄を元に戻した瓜生は、しかし袖の下にある仕掛けが露見した以上、次に死ぬのは俺か連中のどちらかだなと刹那的感情に囚われた。西武に居た頃には、親兄弟からこのような仕打ちを受けたことはないのだ。ついこの前まで睨み合っていた兵隊同士だから、東武に来てからは外様扱いすらされない現実を突き付けられた。怒りの余りつい暗中必殺のエフェクターを作動させてしまったが、これはそうやって見せびらかすものでは無い。見せた以上は、死んでもらうか死ぬしか無いのだから。後悔しても反省しない、それは悧巧な奴がすることだ。
瓜生が昂ぶった感傷に浸っている間に、恭一が簡単な挨拶を先方と済ませる。第十二位から直々というのがどうやら驚きのようで、今度は逆に第十二位本人が非礼を詫びられる側に回った。束になっても機関銃には敵わないと思っているのだろうか。腕っ節と捨て身が取り柄のような男たちは、対弾素材の上着を羽織ることすらも恥じ入るといった有様。第十一位の捨て駒上等という気概すら感じるのは、東武構成員らしからぬ班員だ。東武といえばもっと狡猾で卑劣なのが常だが、義竹は上手く部下を手懐けているらしい。その代表格は大内と名乗った。実は瓜生が勝手に決めつけた通り、野球部出身で陽気な好青年だったのだが。
「仁さんは、今日別行動です。兵隊は俺たち義竹班の六人と、そちらの。」運転手の鈴井を除いた三人、併せて九。車両から出て、西部劇のようなガンベルトを腰に巻き終えた彼ら。どうやら第十一位付きの義竹班は、何らかの拘りで使用銃器は回転式拳銃で統一しているらしい。廉価で扱いやすいとはいえ、これが正気とはとても思えない。瓜生はダブルブレストの上着の背面腰部にホルスターを取り付け、後部座席に仕舞っておいたGSh-18を差し込んだ。子桜は弾薬の入ったショルダーバッグを担ぎ、ルガーを抜いた。綿摘恭一は代替器だったミネベアM9に続いて与えられたAR15を後部座席から引っ張り出した。音に聞くその長物を見て、義竹班の男たちは唖然の様相である。漫画でよく見る日本一有名なアサルトライフルの実物だ、引き取る時には恭一自身も同じ表情をしていた。いや、その時は余りにもあからさますぎて、これからの愛銃にするのが気恥ずかしい思いの方が強かったかも知れない。
「M4カービンをベースにバレルは14.5インチのミリタリーモデルながら、フルオート射撃は勿論、使用弾薬を5.56から9mmパラベラムにカスタマイズして汎用性を上げてある。それだけなら、コルト 9mm SMGで済む話だが、コイツはガス圧作動方式って所が売りだ。ガスブロックを兼ねる照星は9インチミッドレングス。12インチライフルレングスの用意もあるからお好みで。」漆黒のライフルを披露しながら、銃匠さかもとのマスター坂下竜次はそう言った。小型で持ち運びやすいM9はこのまま手元に置いておこうと、恭一は思った。この銃は、それこそ戦争用とも呼べる大袈裟な印象を受ける。その銃を手に取ると、意外にも軽量だ。
「強度と軽度を維持するために、バレルには硬化テクタイト複合鋼を使ってある。流石にそれ以外の部品は炭素樹脂にしたが、高くつくよ。」自信を持って硬化テクタイト複合鋼が扱える職人は国内でも指折りである。素人が此奴を使って殴っても、相手の方はあまりの軽さに戸惑うことだろう。この銃匠、表向きはお好み焼きが楽しめる居酒屋を営んでおり、その特殊合金は此処の鉄板やヘラにも使用されている。銃を構え、高くマウントされた光学照準器を覗く。
「銃床は楓。レンズはニコン。此奴はサービス。」M203がテーブルに乗せられた。なるほど、だからわざわざガス圧作動方式と言うことか。しかし、こんな物までくっ付けておいたら、味方から使うのを期待されるようになるからダメだ。擲弾発射器の二つ名は遠慮したい。持ってきた分の金を払い、残りは後日連絡してもらう事にして、店を出た。
市役所出張所の海堂は、届け出された新規登録銃器を見るなり怪訝な顔をした。本来米国で民間向けに販売されているAR15は、単なるライフル。子桜達が持つようなハンドガンとサイズこそ違えど、どちらの性能も一発ずつ手動で引き金を引く必要があるという点で同じだ。しかし、添えられた銃籍登録申請書は黄色の用紙、特殊の二文字が赤字で印刷されている。この銃は一度引き金を引けば、連続射撃が可能な改造銃という事だ。同じ型で軍用のM16がおいそれと手に入る筈がないのだから。この点に関して厳しい規制のある国内に於いて流通経路なぞ皆無だ。よしんば入手できたとして、いずれは細かい交換部品まで用意できなければならない。にもかかわらず、この銃の匂い立つような艶やかさは何だ。前回届け出された、陸上自衛隊のお下がり染みたM9とは訳が違う。そうこう考えている間に、受け皿へ免許が提出された。この通りに従うしか、仕事のやりようがないのだ。『アンタ、こういうの初めて?』とは、まさに今、海堂自身が置かれたこの状況に他ならなかった。
瓜生達三人はというと、乗車前の昼、事務所でしきりに触らせてくれだの写真を撮らせてくれだのと騒がしかった。特に子桜は、綿摘家に伝わる武術がなんだの実包の呼び名の由来がかんだのと興奮冷めやらぬ様子で捲し立てていた。鈴井の琴線に触れたのはやはり、この銃を所持しているのはデュークがどうだのパチーノがこうだのと、気持ちは分かるが的外れな比較ばかり並べ立てられた。
こんなに早く装備する機会が来るとは、と綿摘恭一は自身の皮肉に苦笑する。何年かすれば、この銃から離れられないような、兄弟以上夫婦未満の関係になっているのだろうか。想像出来ないし、実際その別れはすぐに訪れるのだが、どちらも彼には思いもよらない。見る者を様々な表情に惑わす兵器を肩に担ぎ、彼は門へ向かう。アンデルセン公園北ゲートは半壊しており、侵入者を拒まない。第十一位付きの男達はあまりジロジロと機関銃を見ないようにしながら、先ほどの小競り合いでは第十二位側に華を持たせる形で終えて良かったと思った。先日の打ち合わせでは、ここをずっと前進できれば芝生の広場があるとの事だ。大規模な攻防になるとすれば、それ以降だろう。がらんどうの廃屋となったジェラート売り場周辺の索敵を済ませる。前方遠くに馬鹿でかい像が立っているのが不気味だった。
それは、平和を呼ぶ像。昭和六十一年、船橋市民が世界の恒久平和を願って、平和都市宣言をした記念に建てられたものだ。願いは残念ながら届かなかった事になるが、その像は今から始まるであろう戦火を拒むかのように屹立している。燃え上がる太陽を主題にしたと一目で分かる意匠も、此処船橋に於いては悪夢からの使者以外の何物でもない。この一線を超えたら後戻りできないと、誰もが思って固唾を飲む。平和を呼ぶ像が纏っている、そう思わせるだけの異様が、いや威容が彼等の胃の腑へ一つまた一つと石を入れてくるようだ。おそらく、一人の男を除いて。
「おー、芸術は爆発だの人が作ったのか。ボス、グレネードランチャー無いんすか。」碑文を読んだ瓜生昇が面白半分に軽口を叩く。無かった事にしようとしていたM203の事を指摘されたようで恭一はギクリとした一方、この発言には義竹班の強面一同も呆れ顔となった。野生児の好奇心だなどと好意的に解釈する者はおらず、その場に応じた行動が取れない社会からの落伍者の認識が、第十一位側からなされた。
「ねえねえ。」あまりにも場違いな少女の声が、彼らの一瞬の気の緩みと言う寝耳に水を差し、肝を冷やされた全員が息を飲む。そちらを振り返ると、美しい一輪の黒百合の様な少女が佇んでいた。13歳とも8歳とも見える容姿。襟の白い、黒のワンピース。手を後ろに組み、上半身を楽しそうに揺らしながら、満面の笑みをこちらに振りまいている。
「かくれんぼしましょ。」厄介事は何故連続して起きるのかと、第十一位付きの班長、大内は思った。従来の薄情で暴力的な東武の構成員なら、目撃者として始末してしまうだろうが、彼らはそうしない。ただ、この少女が好奇心で付き纏って離れないとなると、班は壊滅しかねない。あるいは、抗争に巻き込まれて死なれでもしたら寝覚めが悪い。そんな事くらいは理解できるから、この娘を門から遠くに離して戻って来ないようにしなければならない。だが、義竹班の男たちが少女に対応するまでもなく、本日一番の厄介者が早速獲物に喰らい付く。
「やあやあ。これはこれは可愛らしいお嬢ちゃん。カークティビャザヴート?なんだそのツラは、かくれんぼはもう始まってるんだ。見つかったら射ち殺される、死んだら終わりのかくれんぼが。ほら、俺が目をつぶっている間に行けよ。ひとーつ、ふたーつ、」これに肝を冷やして、あどけない少女はすぐさまこの場から逃げ去るかと思いきやそうはならない。浮かべていた笑顔は今や鬼の様な形相となり、目を瞑って数え始めた瓜生の額に穴が空くかという程睨みつけている。その表情は先程までと打って変わって、顔中に深い皺が刻まれているように見える。第十一位付き達は、これで良いのだろうかとも思いつつ、厄介事は厄介者に任せて置こうと決めた。一方で第十二位側の判断はそうではない。おそらく数秒後には、ひと昔もふた昔も前のヤクザ者の背中に彫られた不動明王が如き形相でガンを飛ばしている少女と、一度言ったら撤回しない天才と狂人の狭間を揺れ動くやじろべえとが目を合わせる羽目になる。その状況を飲み込み次第、瓜生はGSh-18を抜き撃ちにするだろう。まだ付き合いの日が浅い綿摘恭一ですらそれくらいの予想がついた。
「お姫様ご機嫌よう、御伽の国に現れた貴女は紛れもなくここの姫君。どうか此奴めの無礼をお許しください。私めは子桜殉、こちらにいる騎士殿の衛士を務めておりますれば、ここは危のうございます。」狩人の反応で瓜生の絡みに割って入り、子桜は俺に芝居を合わせるように目配せした。俺は、彼女と同じ目線まで腰を落とし、簡単な自己紹介をする。綿摘恭一、三十三歳、趣味は読書。俺の声も届かないような満足げな表情をして、少女は子桜に向けて笑みを浮かべている。それが俺の目には、まるで娼婦のような妖艶さに見えて不気味だった。何故そのように見えるのか、その時は見当もつかなかったが。
「ねぇ、おにいさあん、かくれんぼしましょ。」一際甘い声を出して子桜を誘う。
「姫君、今の我々がその大役を仰せつかるには些か荷が勝ちすぎておりますれば、後ほど時間ができました折にお望みのまま。」義竹班の男達も、話している本来の意味が判然としないこの会話を通して、子桜殉と名乗った男が演じる役回りが何を意味するのか分からずにいた。瓜生は瓜生で、目を瞑ったまま数えるのを止めて待っているこの状況を、自分自身でもよく分からないでいた。それでも目を瞑りながら、この状況にさらに子桜が介入したという事は、自分の立ち回りが賞賛されて然るべきだと確信したのではあるが。もしかしたらこの後、二人で手を打ち鳴らし合えるかもしれない、と。
少女はにこにこした表情で、門の方へと去って行った。
「殉君、もう目え開けて良い?」
「キスするわけじゃねえから早く開けろ。」目蓋を開いた瓜生は、子桜が片手を挙げているのを見た。その手をピシャリと打ち鳴らし、そのままポケットからドライバーを一本出して咥え、美味そうに火を付けた。
ちょうどこの場所で、道が分かれている。直進する本道と、右手に折れる路地は道幅が狭く木々が繁っている。義竹班一同は、ここで二手に別れる提案をした。我々の厄介払いをしたかったのだろう。本隊が正面から押し、遊撃隊は搦め手から隠密行動で、最終的に挟撃しようという算段だ。敵の主戦力を十分引き出した上で、機関銃の一斉掃射が最も効率的だった。戦力的にそれが最善だったし、綿摘達一同で行った先日の打ち合わせではそちらからの迂回路も想定していたため、二つ返事で受け入れる。こちらとしても、鉄火場に対弾装備すら着て来ない命知らずと行動を共にするのはぞっとしない。
「アンタらが、ここぞの時に来てくれることを期待してるよ。」警戒しているのか、波風の立たないような指示が出されて両班動く。
別れてしばらくすると、発砲音が聞こえた。遠くに乾いた音が交互する。六挺の回転式拳銃は支障なく働いているようだ。彼らは、効率的な陣形で前線を押し上げて行っているらしい。こちらは、木々の林の中を進む道ながら、守備の兵隊はどうやら配備されていない。この進路が、我々第十二位側の迂路ではあるが、背面からの奇襲を可能にする一縷の光明となる筈だ。しかし、第十一位付き義竹班の銃声が、この道を進むにつれてどんどん遠のいていくのは若干不安ではある。十分に警戒をしながら、極力最大限の進度で先を急ぐ。分かれた道を、左方向の内回りへ。天気が良く、木漏れ日が快いと思わずにいられない。
義竹班の一同は、像からすぐ先の、枯れた泉を左面へ展開。廃墟になった売店で、駄弁っていた旧西武残党を始末した。この銃声に対する反応は、流石に旧西武と言わせるだけのものだった。そこからは進度を落として、しかし着実に前進していく。タイル張りになっている段々から先へと向かうには、開けた地形が防衛側の有利ではあったが、六人は互いを護るような行動を心がけていた。それは功名や野心からではない。義竹仁の顔に泥を塗らないよう、この日の仕事を終えてから、全員で祝杯を上げるそのためだけに鉄砲を扱っているのだ。およそ東武の構成員らしからぬ毅さを備えた、組織の今後に一石を投じる働きぶりである。すぐ先の小屋に居座る数名の男たちを、外壁から窓ガラスまで纏めて蜂の巣にし、そこへ班でも腕の立つ二人が突入する。ここを押さえ、残るは西側半分メルヘンの丘ゾーン。実際のところ射撃訓練場以外での発砲は嘗て経験したこともなく、修羅場というのは初めてだったが、第十二位の加勢なぞ頼りにせずとも作戦は順調に運んでいた。
その頃第十二位一同は、荒れ果てた散策用の林道をぐっと左に折れ、一度は遠くに聞こえていた銃声の元へと再度近付いて来た。園内の看板に、自然散策ゾーンと区分されているだけあり、管理されなくなって久しい今は暗く鬱蒼とした樹林だ。警戒すべきなのは、西武残党による文字通りのアンブッシュ。幸いにも、ここまでは全くの手薄で、進行速度は極力早めることが出来た。義竹班は健在だろう、発砲は絶え間無く続いている。何度かあった小径への分岐ではなく、四叉路に差し掛かったその時、銃声が一斉に鳴り続け、しばらくしてピタリと止んだ。大勢で連発する必要があったのは、どこかの拠点を抑えるためだろうか。合流を急ぐか、側面攻撃のタイミングを掴むか、綿摘恭一は戦略上に於いても岐路に立たされている。しかし今は合流を見送り、銃声の方角を迂回するように、水溜りのような小さい池の間を縫って進行。あれだけの人数が、ここで全滅しているぐらいなら、もう尻尾を巻いて第十二位側だけでも逃げた方が良い。それに、これだけドンパチが続いた後だから、西武の残党はいよいよ警戒を強めて抗戦するだろう。側面攻撃はその時を待てばよい。天気が良く、木漏れ日が快いと思わずにいられない。
アンデルセン公園を東西に分断しているのが、南北に延びた太陽の池だ。この上に架かる幅六人強の橋が、唯一この東西を結び付けている。この橋は長く、位置取りも高い。義竹班の大内は警戒を強めた。順調だったのはここまでだ。今までは不意打ちで圧せたが、これからは徹底抗戦の様相を呈するだろう。おそらく旧西武の拠点と見える、正面向こうにそびえる巨大な風車が持つ威容に気圧されそうだった。馬鹿げている、ドン・キホーテって柄でも齢でも無いというのに。気力を奮わせて脚に力を入れると、右手前方から銃声。壁を白く塗った平屋建てからのものだ。橋の手すりは柵状で、銃弾からの防御には全く期待できない。平屋の周囲には椅子やテーブルが散乱していることから、元々食堂か何かだったところだろうか。それならば、あそこでも大勢が拳銃片手にこちらの動静を睨んでいるはずだ。そこからまとめて誘き出すことができなければ、折角の機関銃も意味を為さない。
「散開!あの建物からの死角に隠れろ。」
幸いにも平屋は下手でこちら側には丘があり、その上で伏せれば銃弾は難なく凌げる。冷静に対処できそうだった。第十二位の到着を待ち、機関銃で屋内の掃除を任せるのも良さそうだ。作戦の幕引きまでの見通しはついた。ただ一つ、そびえる風車でどのような立ち回りを演じるかを除いて。
綿摘班一同は散策路から外れ、向こうに見える広場へと急行していた。公園東側は先ほどの銃声から察するに、既に義竹班が一掃し終えているはずだからだ。急いでいる理由は、さっきまでとは異なる銃声が遠くで、おそらく公園西側で絶えず鳴っているからだ。力強い銃声が、一秒弱ほどの間隔で続いている。一体、何発撃っている?恐怖のつり橋わたり、綱わたり、ネットトンネルくだり。焦れば焦るほど、向こうの広場までを隔てるアスレチックに足をとられる。ネットとびつき、モンキーわたり、ユラユラネットわたり。ヘビースモーカーの瓜生はゼイゼイ言いながら、何やらブツブツと悪態をついている。一方で子桜は器用に四肢を使って潜り抜けているようだ。V字つり橋わたり、足かけさかさま横進み、ターザンうつり。これで東側ワンパク王国ゾーンに合流できた。ちょっとした達成感を噛み締めながら、額の汗を拭う。
「瓜生が追い付いたら、俺たちはあの橋から西側へ向かいます。ボスは先に、そこのボートハウスから船で裏手へ渡って下さい。」子桜から挟撃の道筋を示され、それに従う。強い銃声は止んでいた。
その頃鈴井瞬は、北駐車場から早々に移動を終え、千葉県立船橋県民の森の自然を満喫していた。ここまで車で一分、目と鼻の先にある。どうせ連絡と回収なのだから、その効率を最大限に発揮するためと称して、束の間だけでも鳴り響く銃声や硝煙の臭い、人間どもの雑念から離れようとした。こういう事全てをひっくるめて任務と捉えると、なかなかどうしてこの現場も悪くない。杉林をサッと横切り、広場に出る。出発前に淹れたコーヒーが魔法瓶の水筒に入っている。リュックサックから組み立て式のコンパクトなサンセットチェアを出し、組み立てる。これの座り心地は抜群だ。実はこの日のために、午前中の食事は果物とヨーグルトという、簡単なブランチで済ませていた。ここで数枚の食パンにマヨネーズを塗って食べるためだ。
都内で一人暮らしのビジネスマンが昼に食べたら自殺でもしたくなるように思わせるようなこのメニューを、喧騒とは無縁のアウトドアでやることに大きな意義があるのだと鈴井は考えている。他に誰もいないこの場所で、他のメンバーにも知らせずに、孤独を噛みしめに来ているのだ。さらなる味付けと言っては何だが、マヨネーズはハンドブレンダーで自作してきた。材料を全て常温にしてから混ぜたので、美味そうに見える。全く、心が洗われるとはこの事だった。
『作戦終了の通信が入って無線アラームが静寂を打ち破るまで、ここをキャンプ地とする。』心の中でそう呟いて、愉快だった。
その他、通信傍受用の計器類は作動してはいるものの、ラジオ番組ほど熱心に耳を傾けようという気も無く、そのため行田にいる軍閥から斥候が放たれていることには結果的に気付かなかった。どうせ野次馬が来ているだろう、程度に認識はしていたのだが。そんな事、今はどうでもよいのだ。スーパーの食パンは柔らかく、マヨネーズは味が濃く、コーヒーは酸味が良く、陽光は空高く。自身がこの環境に溶け込んだかのような一体感に浸っている。だから、瓜生達の殺したり殺されたりという役回りにだって感謝の念が自然と湧いてくる。通信装置を使えば、彼らの状況は分かる。だが、今はその様子を想像するだけで良い。仮に状況が悪かったとしても、こちらまでドンパチに参加して生還者ゼロとするわけにはいかないのだから。
一方、子桜と瓜生は、静かにボートを漕ぐ綿摘恭一を眼下に見ながら、太陽の橋を慎重に渡っていた。走れなかった理由は、橋の中央にタンクトップを着た男の死体が一つ有ったためだ。うつぶせで倒れているから顔までは定かでないが、背格好から大内ではないかと予想される。背中から心臓付近を撃たれたか、赤く染まったシャツの周りに大きな血溜まりが出来ている。他の連中は無事だろうか、そう思った瞬間に気付いた。
「こっちに頭を向けて倒れてるってことは、敵に背を向けたところを撃たれたって事だ。逃げようとしたか?」まさか既に第十一位付きの班員は全滅しているのでは無いかと察し、子桜と瓜生は目を合わせる。
事実、平屋を警戒して丘の上で伏せていた義竹班一同は、気配なく風車小屋から出てきた男によって、一人々々が虫けらのように殺された。一面の凄惨さは、先ほどの大内の比では無い。手足が千切れた者、内臓が飛び出した者、顔が半分吹き飛んでいる者。あるいはそれらを併せた者。この光景を見て、子桜は未知の脅威に対する報道精神に火が付き、瓜生の心臓はこの邪悪に対する静かな怒りに覆い尽くされた。丁度その時、綿摘恭一の機関銃が向こうの白い壁の建物で唸りを上げはじめた。
「これをやった化け物があの建物に居ればボスが危ない。」そう言い終えるか否かの瞬間、子桜の視界に男の姿が映った。
その様子に気づいた瓜生は、サッと銅像の影まで飛び退いて先に発砲した。男は、まさに銃を構えようとしているところだった。一発、二発と聞こえた銃声は、子桜の身体には当たっていないらしい。冷や汗と胸の鼓動が煩わしいが、息つく暇もない。三発、四発。瓜生の援護を受け、何とか子桜は、手近な花壇に咲いた花々の中へ身を隠すことができた。舞い散る花弁は、自分がそうさせたのか銃撃によるものなのか分からない。五発、六発と絶えることなく、子桜の方へ銃弾が浴びせられる。地面をのたうつように、対弾繊維を編み込んだジャケットを砂だらけにして、何とか弾に掠らないように遮蔽物に向かって動いた。瓜生が、
「デザートイーグルだ!」と叫んだから。
およそ5mの高さを持つアンデルセン像の裏に隠れた瓜生からは、敵の様子が良く把握できた。グレーのソフト帽を被り、身に纏うのは漆黒のトレンチコート。年季の入った長い顎髭は白髪の方が多く、右目には伊達男かくやと言わんばかりの眼帯をした偉丈夫。鼻持ちならないジジイが向こうへと、両手の銃を交互にブッ放している。十一発、十二発。執拗に、追い詰めるように子桜に銃撃が続いている。そんな事は考えたくないが、あの二挺拳銃がどちらも.50口径なら装弾数は七発。もう撃ち止めだ。両手の塞がった状態で、弾倉の再装填をどうやるつもりだ、呆けジジイ!
男はアンデルセン像に向けて発砲するのを躊躇っているのか、ずっと向こうへばかり射撃を続けている。十四発目の銃声が確かに鳴って、間。
「殉、今だ!!」十字砲火を仕掛けてジジイを殺る。祈るのは、子桜が既に始末されていないこと、それだけだった。
「応!」体勢を整え直した子桜が、銃声がしていた方へルガーを構える。その老人と目が合った、気がした。実際には目を合わせてはいない。右目には眼帯が当てられ、左目は帽子の鍔に隠れているから。いや、弾切れになったはずのデザートイーグルに目が釘付けになっていたと言う方が正確かもしれない。
『デザートイーグルだ!』そう言ったじゃねえか、昇。何で両刀遣いだって言わねえんだ!子桜は、鉄球クレーンの衝撃染みた銃声から、逃げ惑うばかりで精一杯だった。再装填が一度あったのだと思いながら、銃声の数を数えていた。だから、その得物を両手にそれぞれ持っているという、今の光景を急に信じるわけにはいかなかった、何としても。今、この光景を受け入れたら、何でもありになってしまうからだ。それはおかしい。あんな物を両手撃ちが出来るはずがない。そして、その一方で、どうしても認めざるを得ない、或る一つの伝説を思い出した。
この界隈で“ウィザード級”と言えば、超一流の暗殺者を指すが、その由来は、“魔法使い”と呼ばれた綿摘壮一の通り名、ザ・ウィザードに因む。尤もその名は、結婚後に姓が綿摘に代わる以前、刈根壮一が三十歳前後で呼ばれていたものだが。そして、当時の船橋に居たもう一人のウィザード級、その腕力は魔力仕掛けと称された、百の通り名を持つ“戦神”こと大典而丹。二十歳以上も歳の離れた綿摘壮一を、兄弟と呼んだ男である。六十がらみの綿摘壮一が引退だなんだと言っていて、八十を優に超える大典而丹が、現役さながらの銃撃戦を演じている。
ミイラ取りの心得は?ミイラになるな。深淵を覗く時?深淵もまたこちらを見つめているのだ。では、伝説の殺し屋-グランド・アサシン-と対峙するときの心得は?自問自答する子桜を、瓜生が撃ったGSh-18の銃声が現実に引き戻した。応、今だ。弾切れの二挺拳銃に、もうこれ以上有利な状況を作らせるわけにはいかない。大典の右手に握られていたデザートイーグルは、今その足元に落ちている。そうだ、棄てるしかない。ルガーの弾丸は、盾代わりに出された左腕の袖に当たるだけ。もっと精密に狙わなければならない。大典の右手はトレンチコートの懐へ。あるいは、瓜生の弾丸が、奴の後頭部に命中するのが速いか。しかし奴は、大典は何をしている?翻ったトレンチコートの裏地は、どこかで見覚えがあった。
大典は右手に持った銃を棄て、コートから同じ銃を取り出して安全装置を外した。次に左手の銃を棄て、すぐに右手から受け取り、空いた右手は先ほどの動作をもう一度繰り返して安全装置を外した。こんな動きを見ている間も、二人は必死に射撃を続けている。それでも、弾は対弾繊維のコートに当たるばかりらしい。子桜は綿摘恭一の機関銃が駆けつけてくれるのはまだか、祈りながら引き金を弾いている。
ところで裏手にいる瓜生は、デザートイーグルを二挺とも手放したこのジジイはやはり呆けているらしいと思った。撃ちたい放題はこっちの方だ、と瓜生は思う。どう言ったわけか、律儀にもこちら側にあるアンデルセン像には傷を付けられないと見えるらしい。子桜には悪いがこのまま囮になってもらうしかない。殺るのは今、俺しかいない。
子桜は、大典の手元に新たに握られた二挺のデザートイーグルに戦慄した。また、逃げなければならない。形勢逆転の機会は逸した。もう一度、死に物狂いで遮蔽物へと逃げ切らなければ。十四発の弾丸、次は避け得るだろうか。もしも生き延びられたら、その次にこそ勝機はあるか。ただ、生存本能だけが、大典が羽織るトレンチコートの裏地のタータンチェックを思い出した。
『四次元トレンチ・・・。』イギリス軍が第一次世界大戦以来、国内で持ちうる最高の職人芸と現代科学の粋を集めてもなお、実用化にこぎつけるまでに後百年はかかると言われている兵器。まさか、大典があのコートの中に、無数のデザートイーグルを忍ばせているのだとすれば。勝機無し。前へ伸ばし切った両腕を力ませた大典が、その手に握る二挺拳銃にグッと力を込めた。ようだった。ハッキリと見て分かったのは、デザートイーグルの・・・遊底が滑った事だ。
『えー、死んじゃう。嫌、死んじゃう。Yeah,死んじゃう。遺影遺影遺影遺影。』鳴っているギターの旋律、いや戦慄。これは走馬灯だ。自分に向けて、はっきりと銃口が向けられている。引き金を引かれれば、音速を超えた弾丸に五臓六腑を破壊され、血反吐を吐く前に絶命する。だから、もう余りに実感の湧かない連射音を遠くに聞いて、機関銃が間に合ったという冷静な判断が出来ないほどだった。
絶体絶命なのは子桜よりも、むしろ瓜生の方だった。本人がそうと気付いていなかったから猶更だった。それは瓜生昇の背後高くから音もなく飛来した。背中にドン、という強い衝撃。前に倒れまいと本能的に左足を出して踏ん張ったが、不思議と体勢を崩すことはなかった。だがその瞬間、まるで雷にでも撃たれたかのような激痛がし、声も出ない。自分の腹から血塗れになった金属製の棒が突き出て、地面に刺さっているのが分かった時に絶叫した。
「みいつけた。」耳元で少女がささやく。
「カ・・・カークティビャザヴート?」少女の方へ首を向け、絞り出すように発した言葉。己の動揺を悟られないようにするために咄嗟に出た言葉は、却って混乱を証明しているように聞こえるが、二人の間でこのやり取りは成立している。
少女は、立てた親指をグッと地面に向けた。まだ自己紹介も済んでいない小柄な少女から、そう指を差された瓜生はジッと足元を見つめる。銀の槍から滴った血が地面に溜まろうとしているのが見える。だがその血はただ溜まらず、すぐに文字を描き出したのが異常だった。
ᚠᚢᚱᚲ
何語か分からないが、その血文字を見て瓜生の目の前は真っ暗になった。
子桜のルガーが狙いをつける相手もデザートイーグルを構えていたことから全て諒解したものの、あれは大パパじゃないか、と綿摘恭一は機関銃の引金を絞りながら思った。父親の兄貴分、だから大パパ。窮地を脱した子桜が、向こうで何か叫んでいるが、銃声で掻き消されて何も聞こえない。デザートイーグルの銃口は今や、恭一と子桜それぞれに向けられている。が、二丁拳銃の凶手もまた、乱入者の正体を察したようだった。だから、攻勢はより苛烈になり、両手のデザートイーグルはまた放り棄てられた。
船橋東武第十一位義竹班を救う迄には間に合わなかったものの、綿摘恭一の側面攻撃は絶好だった。それは間一髪で子桜を救い、ひいてはピンで留められた虫のようになった瓜生を救う事にもなったから。当たれば死ぬ.50口径の銃と秒間十五発の機関銃との相対は、熾烈な膠着状態に至る。
行田駐屯地から動静の偵察に来ていた二人組は、童話館の屋根に張り付いて、一部始終を見ていた。しかし、通信機器を使用した報告が仮に公園内外で傍受された場合、存在を知らしめることになるためあくまで見ているだけだ。命令が届くこともないから介入もしない。習志野軍閥の特務に就くエージェントWは、帰還用の車内で待機しているスゥと代わっておけば良かったと後悔している。彼は、黙ってじっとしていることに苦痛を感じる性質だった。
地面に槍で磔になった男は動かず、少女から嬲られるがままになっている。その少女の足元に駆け寄って跪いた男は、その手から銃を捨て何かを訴えているようだった。手を広げて何やらわめいているのを、少女が見つめている。大典の銃口がそちらへ向かないように、射撃の手を緩めない綿摘恭一。この状況を主導しているのは誰か、はっきりとしない。
「ソゥ、どう見る?」Wは右隣で腹這いになっている男に訊ねた。
「何とも。ただ、あの老人、ウィザード級の噂通り只者じゃないですね。」
「ああいうのが船橋に居るうちは、俺たちがする仕事もまだ半分で済むんだよ。」
「共喰いじゃないですか。」
「二代目は免許持ってるだけだ。」
「それでも張り合ってますよ。」
「生きてるうちに見てきた射撃の弾数を上回っちまうんじゃねえか、これ。」
「ハハハ、駄目ですよ。」ソゥと呼ばれた男は、Wの感情を先読みして諫めた。どうせ自分も混じりたいと思っているはずだからだ。「アサルトライフルとデザートイーグル二挺、先に弾を切らした方が死にますね。」Wの装備について触れると反発されそうだったので、話題を逸らす。彼らはちゃちな拳銃しか携行していない。
「矛盾、だな。あの故事は結局どうなるんだったかな。」
「ドラゴンの尻尾をくすぐるようなもんじゃないですか。」
「デーモンコアだ、それは。槍から目を離すなよ。」
無駄口を叩いている様でいて、二人の男の表情は真剣そのもの、と言うよりも緊張し切っていた。しかと目に焼き付けて生還し、報告することが任務だから、その緊張感を紛らわすために口を開かずにいられなかったと言うのが真実だ。瞬きも極力しないようにして、その光景を見届けている。大典がかぶっている中折れ帽が宙に舞った。
再装填を繰り返しながらAR15を撃ち続けていた綿摘恭一は、突風が起こったのかと思った。だが、帽子が脱げて露わになった素顔からは眼帯までもが外れ、くるくると錐揉みしながら落下していた。それまで眼帯に覆われていた瞼からは、鮮血が太い筋となって流れ出ている。鳴り響いていた銃声で、何が起きたのか誰も分からなかった。ただ、少女だけが、雷に撃たれたように身体を強張らせて、大典の方を凝視した。彼女はもう、まさに虫の息となっている瓜生も、無様な時間稼ぎのような命乞いをしている子桜のことも眼中にない。
大典に正対している恭一は見上げた。子桜は少女の視線の先を確認した。屋根の上の偵察員は仰向けになってようやく、その脅威が背後に迫っていたことを知った。半キロ先、300mほど上空に静止していた一機のヘリコプター。それは今、尾翼をこちらへ向けて南西方向に飛び去ろうとしている。
『狙撃成功、帰投する。』公園敷地外の路上に停めた車内で、ヘリコプターの通信を傍受したスゥだけは確かに聞いた。しかし、現場の様子を見ているわけではないので、狙撃と言う言葉の意味する所は判然としなかった。その後の『部下と鋏は使いようですよ。』という発言の意味するところも不明だった。とは言え、目の前でそれを見ていた現場の人間たちですら、何が起きたのか断定することは出来ない。
『恭ちゃん、スナイパーに狙われたらどうする?』遠い記憶、父から問われた言葉を急に思い出した。分からない、考えたこともない。あの時、父は自分に何を伝えたかったのか。
三十年以上前、刈根壮一という一人の殺し屋が伝説になった。当時、非合法組織が群雄割拠の首都圏はさながら世紀末の様相であったが、繰り広げられていた抗争“第二次環七ラーメン戦争”を一晩で終結させたからだ。ラーメンブームの終焉は、アサシンブームの払暁となった。わずかばかりの生存者や目撃者が、白馬に乗って現れた謎の男の挙動を口々に称え、いつしか彼は“ザ・ウィザード”と呼ばれるようになった。男も女も彼に憧れ、黒いトレンチコートが流行し、スーツの脇に拳銃を吊るすようになった。
そのブームをさらに加速させたのが『凶手の掟』だ。当時、全くの無名だったと言われる記者が、刈根壮一に取材し、その行動規範や哲学を一冊にまとめた書籍である。第一条「命乞いならあの世で言わせろ」第二条「一流の凶手は一流の革靴を履いている」から第三十一条「死にたくなければ墓から出るな」で終わる一冊のルール。サブカルマニアの子桜は当然この古典とも呼ぶべき著書のファンであるし、この界隈で生きるものなら誰もがその概要程度は知っていなければならない。
この書籍の中に「スナイパーに狙われたらどうするか」という題で書かれた章もあった。結論から言えばその内容は、国内での殺し合いは今後一切、狙撃と言う不意打ち闇討ち大量殺人を自粛せよという、凶手としての矜持に訴えかける文章だ。ルールの中にマナーを盛り込むことで、狙撃に対する絶対的弱者を護ろうという刈根壮一の願いが込められていた事を知るものは誰もいないが。本書が広く国民に読まれることで、凶手という存在の地下活動が広く知れ渡り、大衆からの誤解は大いに払拭された。壮一がその生涯を賭して極めんとする刈根流現代殺法は、ここに一つの到達点を迎える。自らがその境界に立つ死線に法を敷いたのだ。それから数年後に結婚、綿摘に姓を変える。兄貴分の大典而丹が親父格になると同時に叔父貴格就任、表舞台から去ったというのは既に述べた通りである。
話を戻そう。つまり、この界隈で狙撃とは最も悪辣であるとされる禁忌であり、現場にいる全員何が起きたのか混乱して分からないのである。
唯一、大典而丹だけが、人生の幕引きを察した。男は背後の風車小屋へと向かって歩き出す。吹き付けた風に弄られて、漆黒のトレンチコートが裾をバタバタと言わせた。それを聞いて、大典は風に向かって語りかける。
「おお、一緒に来てくれるか。」餞別代りと強請られて壮一にもう一着を寄越した時には、そっちなら呆けずに済むだろう、と半ば強引に引っ手繰られたようなものだったが、今日に至るまで頗る健在だった。なぜなら、あの頃の“記憶”があったから。溢れ出すそれのほとんど半分に壮一が居て、残り半分には少女が居る。しかし今は、“思考”にまで費やしている時間は無い。階段を上がり、窓から風車に輪縄をかける。何という事はない、かつて一度は行った動作の通り、それで首を括った。だらんと吊り下げられた身体が、ぶらんぶらんと揺れている。
『カークティビャザヴート?』ロシア語で相手の名を尋ねる際の成句である。ただ一点、二人称が余りにも馴れ馴れし過ぎたため、大いに不興を買っているのではあるが。その少女の名は揺子。瓜生の胴体諸共に地面を穿った銀の槍を抜く。子桜の目には、もうその少女が二十歳を過ぎた、強い意志を持った女性のようにも観えた。
少女が駆け出し、風が立つ。詩が旋律を得るかのような、ふわりとした跳躍。右手の槍は大典の背部から胸へと突き刺さる。肉体という老いた器は空になり、その輝かしい魂が解き放たれて星になる。
朦朧として呻る瓜生を支え、子桜がすぐ目の前の南ゲートへ向けて歩き出す。静寂を破ったアラームに飛び起きた鈴井は、次はたまごサラダを用意すると再訪を誓う。全身に欠損が見られないことを確認し、綿摘恭一はまた煙草に火をつけた。
一足も二足も速く、船橋東武に帰り着いた第十一位義竹仁。第八位の戒備に経緯を報告し、死んで行った者たちの分は、次の要員に気前良く払って貰いたいと告げた。使えるようになるまで仕込むのに時間はかかるが、鉄砲玉どもの学の無さは美徳だ。馬鹿ならぬ、部下と鋏は使いようなのだから。
全てを見ていたスナッフィーこと飯島誠。放置されたかつての親父分の死体からコートを剥ぎ取り、袖を通す。ウッドストックと名付けたお気に入りの鶴橋を懐に忍ばせる。四次元トレンチも今や、便利な嚢に成り下がった。豚の耳に真珠と言っても過言ではない。
行田駐屯地で報告を受けた小林秀英少佐は、ただ一言
「槍は何処だ!」と叫んだ。
「消失しました。背中に刺さって、胸から突き出る事無く消えました。」特務代行大尉W、同准尉ソゥの二人は口を揃えて言った。無いものは無いのだ。少女の行方も分からない。
習志野軍属大佐、永井日出夫から綿摘壮一に直通回線で連絡が入った。会話の最中に自分の声が安堵していると気が付いたのは、我が子の存命によるのか次期第十二位の椅子を回避したことによるのか分からず、その事が輪をかけて愉快だった。しかし、次の話題は不愉快極まりないものだった。
「跨いじまったね。」越えてはならない一線を、だ。狙撃の禁忌を侵した。
「豊臣秀吉の感覚でいると朝鮮で失敗するんです。しかし・・・。」義竹は身動きが取れなくなったのではない。鴨がネギを背負って来たのでもない。ただ、刑死者が頸に縄を巻いて階段を登っているだけなのだ。要は時間の問題だった。
受話器を置き、綿摘壮一は呟く。誰も彼もが分かっていないのだろう。永井先生はもとより、大典而丹その人までもが。
「今日が水曜日って事を、さ。」
さて、死んだのは誰か。
第五章 自縄自吊 了