約束の地、シド。
そんな場所なんてどうでも良い。
彷徨っているうちに、見失ってしまう。
なんにために其処へ向かっていたのか。
其処にはいったい誰がいるんだろう。
月末に区切りとなる仕事をやっと終え、僕は少しホッとすると同時に、未だに抜け切らない身構えるような感覚に身体を痺れさせていた。
一喜一憂も浮き沈みもあった、肉体的にも精神的にもだ。
ふと思い返してみると、この気の遠くなるような多忙感は、八月末に飛び込んだ急な任務を二ヶ月もの間引きずったと言う訳ではなく、どうやら七月上旬から四ヶ月もの間続いていた事であるらしい。
こう言った事に頓着しない性質が幸いして、この難局をどうにか凌ぐ事は出来たけれども、冷静に考えてみて、無意識に倍の期間の苦痛に苛まれていたのだと言う事を思い知ると気が遠くなりそうである。
そのタイミングを見計らうかのように、謎の美女、モツ野ニコ美女史から仕事抜きの場に呼び出された。
場所は日本橋人形町、彼女のお膝元である。
いつもだったら、僕の方で都内の名店を見繕い、彼女の事を引っ張り出すのだが、あんまり僕が連れ回しすぎて疲れたのか、はたまた彼女はそれだけ懐がヒロくなったのか、茅場町から乗り換えてノコノコやって来たのである。
律儀に時間の三十分前に到着したのには理由がある。
不慣れな土地に来る前に、セルフブリーフィングで周辺をよく調べておくのは当たり前だが、一寸気になる場所があったのだ。
小伝馬町の刑場跡である。
僕は、感情赴くままに其処を訪れた。

日比谷線で一駅先にあるが、歩いて街の息遣いが知りたかった。
案の定、人形町にはつい暖簾をくぐってみたくなるようなお店が豊富だ。




しかも、大通りでこの様子なのだから、路地裏なんかは小躍りしたくなるほどだろう。
モツ野女史がどんなお店を選んでくれるか楽しみになる。
そうこうしている間に、堀留町交差点だ。

驚いたのは、お店が見当たらなくなり何となく寂しく感じられたその位置が、人形町と小伝馬町との中間地点だったという事である。
なるほど、日本橋のような場所であっても、町と町とを道がつないでいるのだ。

僕は手応えを感じると共に、約束の時間に遅れぬよう足を早めた。
小伝馬町駅前交差点の一角には、マニア垂涎と言った風な梅干専門店があった。

恥ずかしながら、回る回らないに限らずお寿司屋さんでガリの使い所を分かっていない僕にとって、梅干しもまた同様だから通過してしまう。

目指すのは其処の裏手にある。
朝と昼だけ営業の田蕎麦さんを脇目に見ながら左へ折れると、寺院の外壁に色とりどりの幟が幾つも立っている。
小伝馬町は牢屋敷に処刑場、彼らの残念を弔うために勧進されたそうだ。
大安楽寺、身延別院それぞれが供養を果たしているらしい。
生い立ちや成した事業など詳しくないが、吉田松陰も此処を最期の地とした。
両院の真向かいにちょっとした公園がある。
晩秋の夜闇をわずかなライトが照らしていた。

奥からたくさんの子供の声がする。
目を凝らすと、母親たちは少し離れて座っている。
目を凝らさなくて良い位置には、浮浪者めいたのがちらほら居た。
僕は吸い寄せられるように奥へ向かい、子供たちから少しばかり離れた、誰も使っていない木造りの机に、買ってきた缶ビールを置いて腰掛けた。
僕は青海波をあしらった他所行きのタイを締めて着飾ってはいるが、浮浪者以上の不審者だ。
歩き飲みしているわけではないからジョッキ生にした。
缶詰みたいな開け口を取り去ってから、一緒に買ったサンドイッチに手をつける暇も無く泡が溢れるので、まず一口。

慌ただしい乾杯になるのが難だな。
それは、誰かと一緒であろうと、たった一人であろうと同じなのだ。
その事実を面白いと思えるかどうかだけが違いだ。
ランニングを済ませてから出てきたので、喉の具合もお腹の具合も心地良い。
十一月四日、良い死の日か、刑死者に手を合わせた。
吉田松陰は享年三十、九つで御前講義を成したという、人の倍の期間を生きていたかのような俊英らしい。
僕は死を想っていた。
ケチャップがこぼれるように人は死ぬのだろうか。
そうではあるまい、それは悪い冗談だ。
人には死ぬべき理由があるのだ。
流れ弾に当たって犬のように死んではならない。
さりとて、神の悪戯で無益に生きてもならないのだ、人は。
だが、生きる目的を見失うくらい、目先の利益や仕事を犬のように追いかけていたくはない、そう思いたかった。
一人でいるからこう思うのだろうか。
家庭を持てば、生き方が変わるだろうか。
目的が見出せるだろうか、決して表沙汰にならない生業の僕たちにも。
生業だけではない、呪われた身体のこの僕が祝福されるというのだろうか。
優しい約束の宜敷、そんな暢気な事を嘯いていた頃が懐かしい。
呷った缶ビールの重みが、残り一口だと示している。
端末の振動が僕を現実に引き戻す。
女史からの着信に、小伝馬町にいると応じると、なんと先ほど通過した堀留町交差点がお互いの中間地点になるからそこで合流という事になった。
水天宮通りを引き返し、その交差点角のコンビニ前で待つ。

先の飲酒でお腹はわくわくしていた。
水先案内人のモツ野女史が現れて誘なう。
挨拶もそこそこに、僕は彼女に惹かれて歩き出した。
向きは、通りを直角に折れて北東へしばらく進む。
「ここよ」
店名も読めず呆然とする僕を尻目に、彼女は戸を引いて中へ這入って行った。

案内されたのは四人掛けの円卓。
店内を見渡すと、もう一つある円卓にはワインが何本も並べてあり使用されない様子。
テーブル席が三つ、カウンター僅か。
奥ではシェフが調理している。
「おまかせコースで宜しかったでしょうか」
愛想のよさそうな男性店員にモツ野女史が頷く。
彼女は僕をフレンチに連れてきたのだった。
早速、飲み物を訊かれる。
僕は白ワインを頼んだが、それに合わせて彼女も白ワインを頼んだ。
「ペアリングをご希望でいらっしゃいますか」
ペアリングとは指輪のことでは無いとかなんとか、下らない事を思った。
そう言われれば僕は白も赤も飲みたいのだが、モツ野女史はそんなに飲まないはずである。
その事を伝えると、店員は笑顔で応じた。
「はいこれ」
彼女は紙袋を僕に渡した。
「なにこれ」
「開けて確認して良いわよ」
ガサガサと開けてみれば、これはシャンプーか。
「顔を洗って出直せって?」
「そうまでは言ってないわよ。ただ、誕生日おめでとうって」
「君には言ってないはずだけど」
「言ってなかったかしら、私、凄腕諜報部員なんだけれど」
そのプレゼントが、きっと僕の垢を落として、新しい自分にしてくれるような気がした。
一杯目は洋梨を感じさせる甘みの、淡麗な白で、二人とも気に入った。
モツ野女史のグラスには多過ぎず少な過ぎず、適切な量が注がれた。
僕は最初の一皿が来る前に飲み干してしまうほどであった。

マッシュルームのポタージュと焼きたてのパンが落ち着く。
二杯目はナッツ様の香りが濃厚な白で、はっきりした差異に気付けるので、僕たちはより一層満足した。
前菜はシャルキュトリの盛り合わせ。

一度食べてみたかった豚の血と脂の腸詰、ブーダンノワールは、あたたかくとろりとして、敷かれているパンはさっくり、挟まれたリンゴジャムも味わい深い。
脛肉の角切りをゼラチンで固めたものは、パセリの香りがクセになりそうだ。
胃袋の中に豚足、耳、タン、ひき肉を詰めて縫い直したものはあっさりとしている。
これが、田舎風パテの濃厚さと好対照で特に良かった。
「この前、部署で飲み会があったのよ、随分久しぶりの事なんだけど。そしたら、一次会も二次会も一番の上役が目の前に座って、参っちゃったわよ。周りはヨイショしかしないし、こっちも気を抜けなくてピリピリするしで、結局六杯も飲んで終電間際に帰ったの。神田の大衆焼き鳥屋で四人掛けボックス席三つ陣取ったんだけど、狭いのなんの。母体が関西にあるから、そのお店も関西人には馴染みみたいで、純けいって串を百本も持ち帰る人もいるんですって」
「ふうん」
そんなに飲めるなんて意外だったのだが、彼女が言うには、少ししか飲めないのは気楽でいられている時なんだそうだ。
「それを言ったら、僕なんて一緒に飲んだ時は決まって東西線で居眠りしてしまう。前回なんか立ったまま寝てたし。これも気楽でいられている証拠かな。だって普段は、よほど飲み過ぎでもしない限り、帰りの電車で眠らないからね。」僕はどこぞの酒客笑売には縁がないつもりだ。
入り口に本日予約満席と張り紙してあったが、この頃には全ての席が埋まった。
先にいた年齢高めの四人は一名が女性、歳の離れた男女は女性の方が十以上若い、近場で働いているかの様な見るからにキャリアウーマン然とした女性二人、それと表向きは堅気の企業勤めを装いながら実際はヤクザとしていることの変わらない様な正義の味方だ。
久しぶりの開放感をさっさと酔いに任せてしまいたい。
心なしか、隣に座っているモツ野ニコ美女史の表情が、いつもの美しさに加えて、どこか可愛らしく見えてしまう。
次の一杯はスパイシー過ぎず重過ぎない赤だった。
ふくよかと評されるそうだが、味わいの均衡が逸脱しておらずぎりぎりを踏みとどまっているのが美味い。
あたたかい前菜がもう一皿、ここは豚料理専門店だから、どれもメインを頂いている気持ちになれて僕は嬉しかった。
テリーヌなのだが、大腸、小腸、ガツ、喉を使って作られている。
マッシュポテトが敷かれており、ポーチドエッグが載っている。

割って絡めて頂くと、焼き目の食感も、混成された味わいもほんの僅かに喉の食感がこりこりとしていて素晴らしい。
次が最後となる、ベリーの風味が軽やかで、先ほどに比べてすっきりした酸味の赤。
メインの一皿は、古代種ヨークシャーと、一時期国内で七頭までに減ってしまった満州豚とを交配させた静岡の豚ロースのソテー。
シンプルな調理だが臭みは全く無く、非の打ち所がない肉質。
付け合わせの野菜や茸はどれも濃厚な味わいだったので、お肉と同等の感動を得られた。

脂身がくど過ぎず、女性でもさらりと頂けるので、これもワインに合う。
結局、彼女は僕と同じワインを一口ずつ飲んだ。
ソムリエが気を利かせて、一杯のグラスを二人に分けて与えてくれたのだった。
僕は、もう少し飲みたいくらいの、良い酔い具合だ。
「此処のモンブランが一番好きなの」と彼女が囁いたデザートも、確かに格別だった。
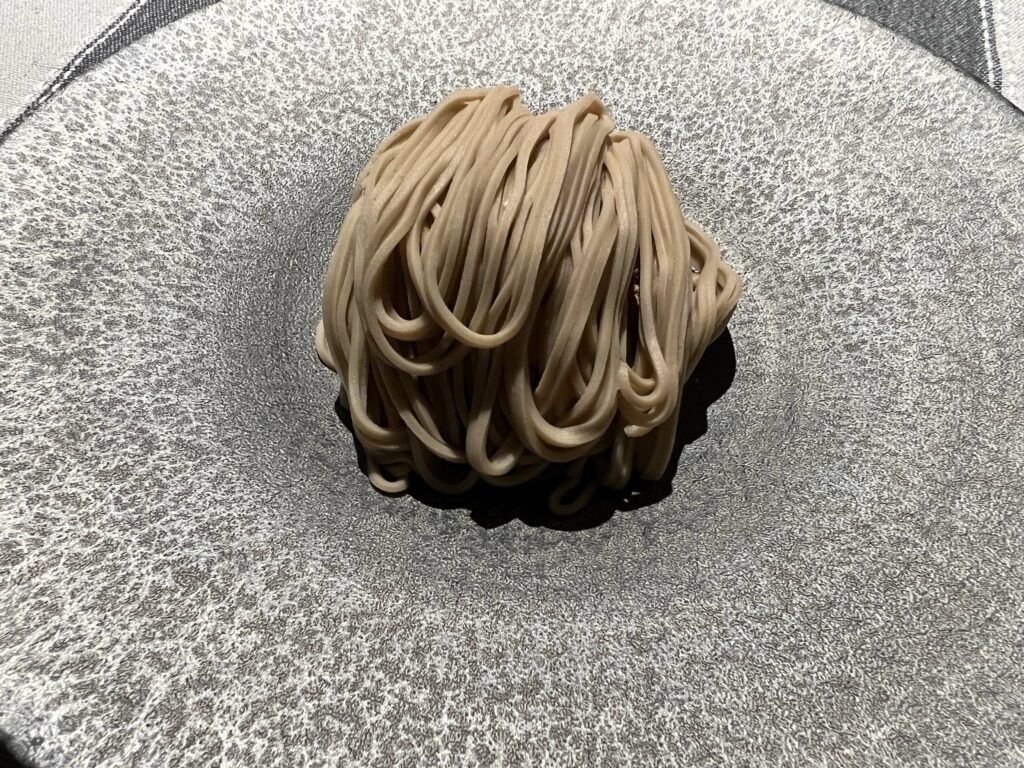
来月は、もう年末だ、いつの間にか。
食後のコーヒーを飲みながら、僕は少し考え込んでしまった。
